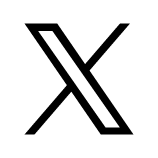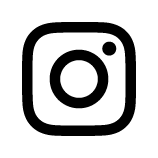第12話/「専門学校から歯科大学へ~けん引者たちの歩みにみる歯科医学史~」(近代歯科・事始めを巡る散歩④)
歯科大学の聖地「お茶の水・水道橋・飯田橋界隈」の道行き途中に我孫子で道草
これまでも述べてきたように、日本の本格的な歯科医学教育の歴史は、1906(明治39)年に制定された「公立私立歯科医学校指定規則」の施行に基づき、1907(明治40)年~1928(昭和3)年までに誕生した「6つの旧制歯科医学専門学校」の存在が基盤となり、開始されました。
6つの旧制歯科医学専門学校とは「①東京歯科医学専門学校/現在の東京歯科大学」「②日本歯科医学専門学校/現在の日本歯科大学」「③東洋歯科医学専門学校/現在の日本大学歯学部」「④大阪歯科医学専門学校/現在の大阪歯科大学」「⑤九州歯科医学専門学校/現在の九州歯科大学」「⑥東京医学歯学専門学校/後の東京医科歯科大学/現在の東京科学大学歯学部」です。
日本の大学歯学部は国公私立を合わせて、現在29校(日本歯科大学と日本大学は歯学部を2カ所で運営)ありますが、上記の6校は現在も「旧6歯科大学(6つの旧制歯科医学専門学校から戦後の学制改革で大学に昇格した6校)」と呼ばれ、その伝統と実績に敬意が払われていることも、すでにふれてきた通りです。
さらに旧6歯科大学のうち、東京に立地する4歯科大学(東京歯科大学、日本歯科大学、日本大学歯学部、東京科学大学歯学部)のキャンパスが集中する、JR中央線の御茶ノ水駅・水道橋駅・飯田橋駅の周辺とその界隈を、本欄では前々回から散歩してきました。
今回はその仕上げのパートとなりますが、その前に少々、遠出の寄り道をしたいと思います。向かったのは、千葉県北西部の住宅都市・我孫子市です。
目的地はJR常磐線・我孫子駅からバスで5分ほどの手賀沼湖畔(手賀沼公園)。手賀沼は周囲が38㎞もある立派な湖沼(利根川水系)で、水域は我孫子市をはじめ、柏市、白井市、印西市(いずれも千葉県)にまたがっています。

手賀沼の畔・手賀沼公園にある血脇守之助顕彰碑。
2m以上ある巨大な石板に後進の血脇守之助に対する謝恩の念が満ちあふれている
我孫子市は東京歯科大学の前身である旧制東京歯科医学専門学校を設立した血脇守之助の生誕地で、手賀沼湖畔の手賀沼公園には、血脇守之助の顕彰碑(血脇先生謝恩の碑)があるのです。
以前から一度訪ねたいと思いつつ行けずじまいでしたが、この機会に、思い切って訪ねました。
近代歯科医学教育のメンター「4学祖」+「東京歯科大学中興の祖・血脇守之助」
御茶ノ水駅・水道橋駅・飯田橋駅の周辺に立地する4歯科大学には、それぞれ、カリスマ性に満ち溢れた「学祖」がいました。
東京歯科大学のルーツである「高山歯科医学院」を設立した高山紀齋(1851/嘉永3年~1933/昭和8年)。日本歯科大学のルーツである「共立歯科医学校」と「旧制日本歯科医学専門学校」を設立した中原市五郎(1867/慶応3年~1941/昭和16年)。日本大学歯学部のルーツである「東洋歯科医学校」と「旧制東洋歯科医学専門学校」を設立した佐藤運雄(1879/明治12年~1964/昭和39年)。東京科学大学(旧東京医科歯科大学)歯学部のルーツである「東京歯科医学校」を設立した島峰徹(1877/明治10年~1945/昭和20年)です。
日本歯科大学の学祖・中原市五郎と日本大学歯学部の学祖・佐藤運雄は、旧制歯科医学専門学校の設立も手がけましたが、東京歯科大学の学祖・高山紀齋はその任を後継者・血脇守之助(1870/明治3年~1947/昭和22年)に譲りました。
また、東京科学大学歯学部の学祖・島峰徹は、東京歯科医学校に医学部を加える偉業を成し遂げたものの、旧制東京医学歯学専門学校に昇格する直前に病に倒れたため、東京歯科医学校の2代目校長に就任していた長尾優(1887/明治20年~1975/昭和50年)が、旧制東京医学歯学専門学校の設立を実施しました。
前回ご紹介したように、島峰徹とほぼ同時期に旧制歯科医学専門学校を大学化する運動を、国に対し展開していた血脇守之助は、島峰徹と同様、自分が設立した旧制歯科医学専門学校の大学化の実現を見られないまま、死去してしまいます。
しかし、その成し遂げた実績は4人の学祖たちに劣らず素晴らしいもので、日本最古の歯科大学である東京歯科大学における「中興の祖」ともされています。
同時に歯科界全体の地位向上にも尽力し、日本歯科医学会会長(1912/明治45年~1916/大正5年)、日本歯科医師会会長(1926/大正15年~1946/昭和21年)などを歴任しています。
特に戦前戦後を股にかけて、日本歯科医師会会長を死の直前まで足掛け21年間に渡って務めた事実は、当時の歯科界全体にとって血脇守之助がいかに重要な役割を担っていたかを、如実に証明しているといえるでしょう。
血脇守之助はまた、教育者という以上に本来の意味でのメンター(精神的指導者・偉大な助言者)ともいうべきカリスマ性についても、4歯科大学の学祖たちに負けないものを持っていたようです。
例えば、血脇守之助は世界的な細菌学者として今日知られる野口英世(1876/明治9年~1928/昭和3年)の才能を早くから認め、野口英世が無名だった時代から手厚い庇護を行いました。
時には野口から手ひどく裏切られたりしても決して見捨てず、野口英世が細菌学者として名を成す基盤を構築した大恩人として、今も語り継がれています。
また、一種の性格破綻者的な側面を持つ野口英世を、世間が見捨てても信じ、支えたエピソードは、まさに血脇守之助の指導者・教育者として不可欠な「見る目の確かさ」「長期的に物事を見据えられる資質」「粘り強さ」などを物語っているのではないでしょうか。
そして実は、血脇守之助の生涯も、野口英世とは違った意味で、なかなか波乱万丈だったようです。
前述のように、血脇守之助は我孫子市(旧我孫子宿時代)に生まれました。JR我孫子駅の前身である旧日本鉄道・我孫子駅ができたのは1896(明治29)年。血脇守之助は1870(明治3)年生まれですから、血脇守之助が我孫子にいた時期(1882/明治15年まで在住)には、鉄道駅はありませんでした。
しかし、我孫子駅の立地する場所は水戸街道の旧宿場町・我孫子宿の中心部に当たります。血脇守之助の生家は、現在の我孫子駅のすぐ近くで「かど屋」という屋号の旅籠(宿屋)を営んでいた加藤家で、生誕時から18歳までは加藤守之助として過ごします。

手賀沼は首都圏では大きな湖沼。
往時からの干拓事業の結果、元の大きさの2割程度しかないとされるが、市民や観光客の憩いの場だ
手賀沼湖畔(手賀沼公園)に現在ある顕彰碑は当初、我孫子駅に直近の「生家跡」に、高山歯科医学院の創立50周年事業として、1940(昭和15)年に建立されました。しかし、その後、駅周辺の都市計画事業に付随して、市民の憩いの場である手賀沼公園の現在とは別の場所に移転。さらに2003(平成15)年、手賀沼公園のリニューアルに伴い、現在地に移転したのです。
守之助の波乱の生涯は4歳から始まります。4歳の時に母を病気で失い、祖父母に育てられることになるのですが、12歳の時には叔父に連れられて上京。年譜によると慶應義塾や東京英学校(後の青山学院)、明治英学校ほか、7校もの英語・英学を学べる学校に次々と通い、柔道の祖・嘉納治五郎が館長を務める講道館で柔道修行までしたそうです。
なんとも凄まじい英才教育ぶり(!?)ですが、その過程で、18歳の折に血脇家の養子となり、以後、血脇守之助となります。
そして1889(明治22)年、最終的に慶應義塾を卒業すると、翌年には東京新報社に入社。新聞記者生活に入りますが、大けがを負ってわずか4か月で退職します。

三条市を流れる日本一の大河・信濃川。
血脇守之助は信濃川の堤を散策しながら歯科医学への道を模索したことだろう
さらに、1892(明治24)年、新潟県三条市(当時は南蒲原郡三条町)で英語教師の職を得て転居するのですが、ここでようやく、22歳の血脇守之助は「歯科医学との出会い」の場を持ちます。
『東京歯科大学同窓会報第397号(2015/平成27年2月発行)』に掲載された同窓生の寄稿の一つに『血脇守之助が三条に滞在しなかったら東京歯科大学の血脇守之助は無かった』(昭和46年卒業・阿部晴弘著)という、なかなか刺激的なタイトルの文章があります。
血脇守之助は三条で出会ったアメリカ帰りの医師・田原利(三条病院院長)と親しくなり、アメリカの医療・医学事情などを聞いて関心を深めつつあった時に、たまたま読んだニューヨーク・ヘラルド紙に掲載されていた「歯科医院」の広告を見つけます。そして、これをキッカケに、まだ日本では欧米ほど盛んでない歯科医師という存在と歯科医学という学問ジャンルこそは、自分が生涯を賭して追求するだけの価値を持つ職業であり「道」ではないかという考えに傾いていきます。
そこで親しくなったばかりの田原医師にその話をすると、大いに賛同されたことから、1894(明治26)年、英語教師の職を辞して再び上京。高山紀齋が設立した高山歯科医学院に入学するのです。
まさに三条での足掛け3年間がなければ、近代歯科界の偉人の1人、血脇守之助は誕生していなかったのかもしれません。
そして、血脇守之助が高山歯科医学院に入学した時期には1894年説と1893年説があるのですが、いずれにしても血脇守之助は1895(明治25)年にあっさり、医術開業試験に合格してしまいます。
高山歯科医学院に入学し、歯科医学の本格的な勉強を始めて1年後ないし2年後の出来事です。この事実一つだけをとっても、「血脇守之助の超優秀さ」は疑いようのないものといえます。
超カリスマの高山紀齋が、自らの後継者に血脇守之助を指名したのも、まったくもって当然と思われます。
4 歯科大学・学祖の1人、佐藤運雄につながる日本の近代歯科医学の祖・イーストレーキとの間接的絆
さて、再び御茶ノ水駅・水道橋駅・飯田橋駅周辺の散歩に戻ります。前々回からの流れで、各大学の周辺を歩きつつ、本欄のタイトルにある「専門学校から歯科大学へのけん引者」たち、すなわち4歯科大学の学祖である高山紀齋(東京歯科大学)、中原市五郎(日本歯科大学)、島峰徹(東京科学大学歯学部)に関しては、分量にばらつきはあるものの、すでに触れてきました。
残るは御茶ノ水駅をはさんで、東京科学大学とは逆側の駿河台に立地する日本大学歯学部と、その学祖・佐藤運雄をめぐる散歩となりますが、佐藤運雄は、実は血脇守之助が講師を務めていた高山歯科医学院時代の教え子(1898/明治30年卒業)でもありました。
そして佐藤運雄は、高山歯科医学院を卒業後、18年目の1916(大正5)年に日本大学歯学部のルーツである東洋歯科医学校を設立し、1921(大正10)年には旧制東洋歯科医学専門学校への昇格を実現。1943(昭和18)年には日本大学学長、さらに念願かなって、1947(昭和22)年の学制改革では日本大学歯学部(旧制)設置の認可についても自ら手掛けることができ、初代歯科長および学部長に就任しています。
4歯科大学のうち、そもそものルーツである歯科医学校から旧制歯科医学専門学校、さらに大学への昇格をすべて手掛けることができたのは、4学祖のうち佐藤運雄だけです。
その佐藤運雄のブロンズ像が現在、日大歯学部付属病院のロビーに展示されており、生前の「温顔」をしのぶことができます。
佐藤運雄はまた、高山歯科医学院を卒業後にすぐ渡米し、1901年にはレーキフォレスト大学歯学部(イリノイ州)を、1903年にはシカゴ大学ラッシュ医科大学を卒業。帰国後に母校・高山歯科医学院や東京帝国大学の講師を歴任しているので、恩師(メンター)である血脇守之助との絆も再度深まったことでしょう(※佐藤運雄はアメリカの大学を卒業したため、医術開業試験の受験はせず、歯科医院の開業免許を授与されている)。
さらに佐藤運雄には、もう1人のメンターともいうべき存在がいます。養父の佐藤重です。そして佐藤重は、なんと、以前に本欄でご紹介した長谷川保とともに、日本の近代歯科医学史にとって忘れてはいけないアメリカ出身の歯科医師、ウィリアム・クラーク・イーストレーキの直弟子・高弟だった人なのです。
日本人による日本の近代歯科医学教育史は、再三述べてきたように、高山紀齋や高山の同志・一井正典などの世代から始まりますが、本欄第3回~5回でふれたように、西洋の歯科医療技術を日本に持ち込み、歯科医師という存在そのものを、身をもって日本人に示したのは、横浜の外国人居留地で開業したイーストレーキ、セント・ジョージ・エリオット(日本人初の歯科医師資格取得者・小幡英之助の師匠)、ハラック・マーソン・パーキンスをはじめとする、主にアメリカ人の歯科医師たちでした。
彼らは外国人居留地に暮らす欧米人たちの歯科治療を行うことを目的に来日しますが、噂を聞き駆けつける日本人の治療も行い、さらには日本人の押しかけ弟子たち(歯科医師志望者、歯科技工士志望者など)も助手として雇用し、実戦的な指導を行います。
日本大学歯学部の学祖・佐藤運雄の養父・佐藤重は、そうした経緯でイーストレーキに学んだ高弟であり、後に佐藤歯科医院を開業し院長に就任します。
当然のことながら、佐藤運雄は自身の養父・佐藤重に、恐らくは子どもの頃から「跡継ぎ」としての薫陶をさまざまな形で与えられていたのではないでしょうか。
その薫陶は西洋の歯科医療の実技や、最新の歯科医学的知識、ひいては歯科医師としての役割・心得についての「訓え」などにもおよんでいたことでしょう。まさに第一の指導者(メンター)です。
だからこそ佐藤運雄は、旧制中学を卒業後に19歳で高山歯科医学院に入学し、第二のメンターである血脇守之助との出会いを果たすと、すぐに才能を開花させることができたのでしょう。
さらに養父・佐藤重のメンターであるイーストレーキから数えれば、3代にわたってつながる「絆(きずな)」の連鎖があります。
その絆の連鎖には、日本における近代西洋歯科医学の夜明けから、近代歯科医学教育の拠点校の一つ「日本大学歯学部」の成り立ちに至るまでの長く濃厚な歴史的時間が、みっしりと凝縮されているように思われます。
血脇守之助の顕彰碑(血脇先生謝恩の碑)と対面した後、JR常磐線・我孫子駅まで乗り入れている地下鉄千代田線で新御茶ノ水駅まで戻り、再び歩き始めた日本大学歯学部の周囲は、小雨模様の平日であることと、周辺に集中する大学や専門学校の入学式より少し前の時期だったせいか、人通りはまばらでした。
しかし、血脇守之助←→佐藤運雄←→佐藤重←→イーストレーキの絆の連鎖がもたらす関係性の妙に、少し興奮していたせいでしょうか。寒さはまったくといっていいほどに感じられませんでした。
日本大学歯学部の学祖・佐藤運雄のブロンズ像は、2022(令和4)年から本格稼働した日本大学歯学部本館1階の附属病院ロビーにありますが、本館の対面にあるレトロな雰囲気の3号館の前には、佐藤運雄の後継者として第2代歯科長に就任した中川大介(後に日本大学歯学部名誉教授、1887/明治20年~1954/昭和29年)の堂々たる風貌を写したブロンズ像も設置されています。
そして、卒業の季節と入学の季節の狭間にあった取材時には、閑散としていたこの界隈ですが、すでに桜も散り終わり、今ごろは歯科医学を新たに学ぶ若者たちでいっぱいになっているはずです。
そんな感慨とともに、4歯科大学周辺における近現代歯科散歩の道行の記を、そろそろ閉じることにいたします。(文中敬称略)
メイン画像説明
東京歯科大学では校舎の新築・改築・移転などの際には必ず、本館に隣接する三崎稲荷神社の宮司がお祓いする。大学そのものが氏子なのだ
筆者プロフィール
未知草ニハチロー(股旅散歩家)
日本各地を股にかけて散歩しながら、雑誌などにまちづくりのリポートをしている。
裸の大将・山下清のように足の裏がブ厚くなるほど、各地を歩きまわる(散歩する)ことが目標。